
個人で飲食店やサービス業、フリーランスとして活躍していた方が亡くなった場合、その相続手続きには"事業特有"の対応が求められます。
たとえば、屋号の扱いや事業資産・負債の整理、青色申告の対応など、通常の相続とは異なる注意点が数多く存在します。
この記事では、個人事業主・自営業者が亡くなった際に生じる相続手続きについて、事業の「継続」「廃止」それぞれのパターンに応じて必要な手続きをわかりやすく解説します。

個人で飲食店やサービス業、フリーランスとして活躍していた方が亡くなった場合、その相続手続きには"事業特有"の対応が求められます。
たとえば、屋号の扱いや事業資産・負債の整理、青色申告の対応など、通常の相続とは異なる注意点が数多く存在します。
この記事では、個人事業主・自営業者が亡くなった際に生じる相続手続きについて、事業の「継続」「廃止」それぞれのパターンに応じて必要な手続きをわかりやすく解説します。

近年、建設業界における企業の倒産件数が増加傾向にあることはご存じでしょうか。2025年1月に総務省が発表した労働力調査では、建設業に従事する就業者が前年483万人から1.24%減の477万人となっており、業界の「職人不足」が懸念されています。
また、就業者は常態的に「高齢化」が進んでおり、2024年の建設業における就業者は60歳以上が驚くことに25%超となっています。加えて、円安進行などの影響により建設資材は高騰しており、複合的な要因が絡み合った結果、倒産が増加しているのです。
本記事では、建設業の倒産が増えている背景について、資材価格の高騰や職人不足の問題を交えながら、建設業の経営成功に向けたリスク対策もあわせて解説します。
みんなの顧問・相続(当社運営外部サイト)を参照ください。
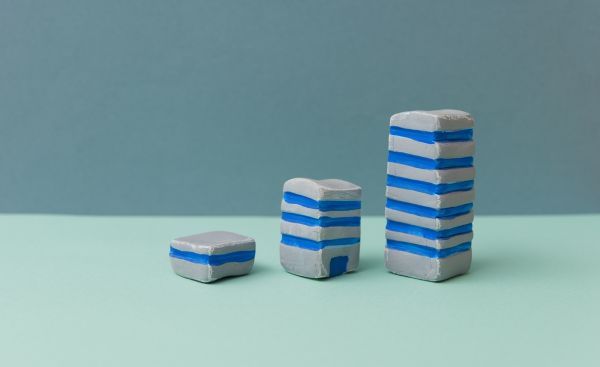
親がアパートやマンションを経営していた場合、その不動産は「収益物件」として相続財産のひとつになります。相続人にとっては「資産」とも言えますが、同時に「管理や手間、借金などのリスク」を引き継ぐことにもなります。
とくに大家業には、入居者対応や修繕、確定申告など、思っている以上に手間のかかる仕事も多く、経験や知識がないまま引き継ぐと、思わぬトラブルを招くこともあります。また、収益物件はお金の価値だけでは分けにくく、遺産分割でもめやすい財産の一つです。
この記事では、親のアパート・マンション経営を相続することになったときに、まず何を考えるべきか、引き継ぎの判断ポイント、遺産分割の注意点、相続後の対応まで、専門家に相談するタイミングも含めてわかりやすく解説します。
みんなの顧問・相続(当社運営外部サイト)を参照ください。

相続人同士で遺産の分け方について話し合っても、どうしても合意できないことがあります。そんなときは、家庭裁判所を通じた「遺産分割調停」が行われますが、それでも意見がまとまらなければ「調停不成立」となり、次の段階である「遺産分割審判」に進みます。
審判では、裁判官が法律にもとづいて遺産の分け方を決めるため、調停とは異なる対応が求められます。本記事では、調停が不成立になる典型的なケースや、審判に移ったあとの流れ、調停や審判における弁護士の役割などを、わかりやすく解説します。
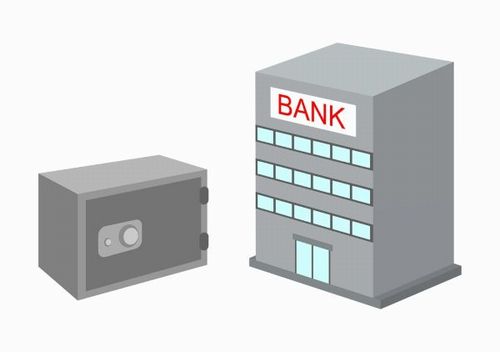
最近、金融機関の貸金庫を狙った窃盗事件が相次いで報道されています。特に、銀行や信用組合の元職員が関与するケースが続発し、利用者の不安も高まっています。
貸金庫は貴重品や重要書類を保管する場所として便利ですが、相続時には開け方や手続きに戸惑うことも少なくありません。特に、貸金庫の中に遺言書が保管されている可能性がある場合、適切な手順を踏まなければ開封できず、相続手続きが滞ることも。
本記事では、貸金庫の相続手続きの流れや、遺言書が見つかった場合の対応について詳しく解説します。
みんなの顧問・相続(当社運営外部サイト)を参照ください。

2024年11月1日から「フリーランス新法(フリーランス保護新法)」が施行されました。この法律は、フリーランスが安心して働ける環境を整えることを目的とし、報酬の支払期限の明確化や契約内容の書面化など、発注企業に対しても新たな義務を課しています。
本記事では、フリーランス新法の概要や、発注企業が対応すべきポイント、下請法との違いについて詳しく解説します。フリーランスと適正な取引を行い、法令を遵守するために、ぜひ参考にしてください。
みんなの顧問(当社運営外部サイト)を参照ください。

近年、カスタマーハラスメント(カスハラ)の被害が増加し、多くの企業が対応に苦慮しています。長時間に及ぶ謝罪要求、高圧的な態度、理不尽なクレームなど、従業員の精神的・身体的負担を引き起こすケースは少なくありません。そのため、企業はカスハラへの対応基準を明確に定め、従業員を守る体制を整えることが不可欠です。
この記事では、カスハラの定義や判断基準、企業が取るべき対策について詳しく解説します。

「相続した土地を持て余している。」
「管理も売却も難しく、負担ばかりが増えていく。」
故人の遺した不動産が思いがけず負担になることは少なくありません。そんなときの選択肢のひとつが相続放棄です。
ただし、相続放棄には期限(3か月以内)があります。これを過ぎると相続した不動産の管理義務が発生し、簡単に手放すことができなくなります。
しかし、2023年に施行された「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、一定の条件を満たすことで国に土地を引き取ってもらえる可能性があります。
この記事では、相続放棄の手続きと、相続土地国庫帰属制度の活用方法について解説します。
不要な不動産をどうすべきか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

会社は、契約書の締結や取引先とのトラブルなど、何かと法的な問題にぶつかりやすいものです。
そういった問題に対して、インターネットなどで調べて自分で対応してしまうと、後々、自身が不利な立場に置かれたり、できるはずだった主張ができなくなるなどの事態に見舞われることも少なくありません。
そういった問題を回避するためには、弁護士と顧問契約を締結することが有用です。
しかしそうはいっても、弁護士との顧問契約をどのようなタイミングで行えばよいのか、顧問契約を結ぶことのメリットはどんなことがあるのかわからないという方も少なくないでしょう。
そこで今回は、弁護士との顧問契約をするタイミングや顧問契約のメリットについて解説をしていきます。